×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
「内科生涯教育講演会」
9月9日、日本内科学会北海道支部主催の第48回生涯教育講演会に参加した。
昭和大学二木芳人氏『感染症の診断と治療、最新の話題』
■難治下する感染症
背景として、医療の進歩により延命、生命維持療法の進歩、医療の場の変化、脳死下移植が増加、骨髄移植が年間4000件を超える、リウマチにおける生物学的製剤、人口の高齢化、様々な合併症(糖尿病、COPD、誤嚥性肺炎)等が挙げられる。肺炎死亡が第3位になった。医療。介護関連肺炎の治療ガイドラインができた。
■耐性菌の話題
・多剤耐性菌(アシネトバクター)の院内感染、「NDM1」新耐性菌を確認(インドから発症)、どんな薬剤も壊すメタロβラクタマーゼが話題となっている。
・インテグロンという複数の耐性遺伝子を効率よく取り込むことができる機序がある。
市中感染に抗菌薬耐性菌が増加している。
・市中感染型MRSA感染症が若年者の皮膚感染が増えている。米国では大流行している。
・市中肺炎では、肺炎球菌、インフルエン桿菌、モラキセラ菌、マイコプラズマ菌、C.pneumoniaeで95%を占める。
・マクロライド薬耐性マイコプラズマが増加している。大人はテトラサイクリンを第一に使う。小児にはニューキノロンを使用は控えること(耐性菌をつくらないため)。マクロライドを使うなら高容量を使う(800mg-1000mg/日)オーグメンチン、フロモックスは大量に使えばかなり有効である(下痢を起こしやすい)。クラリスはインフルエンザ桿菌に耐性が多い(ジスロマックは大丈夫)。
・濃度依存的殺菌:キノロン(一度に大量に投与すること)。
・経口抗菌薬を広範囲に少量を長期間使用することが耐性菌を増やす元凶である!
高知大学横山彰仁氏『慢性気道疾患の診療』
■概観
・COPDと気管支喘息。若いうちは喘息。年取るとCOPD.COPDに対する認知度が低い。認知度を上げるために健康日本21に取り上げられた。
・定義:タバコ暴露、気流閉塞、不可逆なもの。
喘息は喘息症候群と呼んだ方がよい。症状の強さと好酸球性気道炎症と程度の2つの要素で診る。喘息とCOPDは同じ疾患群という「オランダ仮説」がある。どちらか不明のときは喘息として吸入ステロイドを使用すること。
■診断
・COPDは進行性であるが、早期には気付かない。陸で溺れるような辛さがある。タバコに弱い人は早期に禁煙が必要である。症状や画像による診断は遅い。早期発見には肺機能検査がよい。1秒率が70%以下。「肺年齢」という機器が販売されている。
■治療の考え方
・喘息はコントロール状態によって治療する。最小限の薬剤でコントロール状態を維持し、将来のリスクを避ける。まず、吸入ステロイドを使う。
・COPDはいつでも治療可能な疾患である。禁煙、インフルエンザワクチン、併存症の管理が重要。β作動薬よりも先に抗コリン薬を使う。進行したCOPDは増悪をきたす。1秒量<50%、過去に増悪がある例は危険。増悪時のABC.抗菌薬(A)、気管支拡張薬(B)、全身ステロイド(C)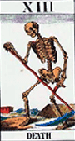
■全身を診る
・3つ以上の併存症があるものが50%。鼻炎、GERDが多い。50歳で1個、65歳で2個。全身性酸化ストレス。糖尿病、心血管疾患(潜在している)、肺炎・肺がん、筋力低下、骨粗鬆症、抑うつ。死因として心血管疾患が多い。頸動脈の動脈硬化が進んでいる(タバコで肺と血管を傷める)。予後を悪化させる。
・COPDの30%に心不全がある。心不全の30%にCOPDがある。選択的β1ブロッカーは安全である。吸入β2刺激薬の使用は要注意である(抗コリン薬がよい)。
■質問
・吸入ステロイドは肺炎のリスクを増す。
・一過性の喘息様症状に吸入ステロイドを使ってもよい。
・喫煙者で呼吸器症状がある患者には、一度呼吸機能検査を勧める。
名古屋大学今井圓裕氏『ネフローゼ症候群の新しい診療指針』
■コホート研究
・巣状分節性腎症;ステロイド抵抗性が60%、パルス・免疫抑制剤が必要、LDLアフェレーシスが有効、日本人の予後は意外とよい。膜性腎症:60%は緩解する。
・微小変化型は再発しやすい。
・死亡例は感染症が原因。過剰な治療が影響。
・ステロイド糖尿病が起こってしまう。
■診療指針
・タンパク尿>3.5g/日(尿たんぱく/尿クレアチニン比>3.5g/gCrでもよい)、浮腫、血清アルブミン<3.0g/dl、脂質異常症。
・思ったよりもステロイド、免疫抑制剤が長期に使われている実態が判明した。
・病態機序としてoverfilling仮説が有力。遠位尿細管でのNa再吸収が亢進。
・治療は、塩分制限:6g/日以下、利尿剤の治療、アルブミン静注は可能な限り避ける、RAS阻害薬を使用。スタチンを使用するかどうかは腎症のタイプによって異なる。
・DVTの予防のためにワーファリンを用いるが、アスピリンについては意見が分かれる。
・膜性腎症の10%に悪性疾患がある。IgGの沈着、足突起のフォスホリパーゼに抗原抗体反応がおこる自己免疫疾患である(日本人では50%)。抗体を減らせば治る。日本人はタンパク尿が少ない。ステロイドパルスは行わない。シクロスポリンを用いる。
・シクロホスファマイドを使用すると、膀胱がんが増える・
・肺炎球菌ワクチン使用、結核のスクリーニング、ニュモシスチス肺炎予防にST合剤を集に2回投与。
・微小変化群:ステロイドが有効だが、パスル療法は不要。再発が多い。
・膜性増殖性腎炎:HCVが関与。確実な治療法はない。
九州大学高柳涼一氏『副腎疾患の最近のTopics』
■原発性アルドステロン症は高血圧の3.3-10%。
・スクリーニングは安静30分後のレニンとアルドステロンを測定。PAC/PRA>200で判定。
・Kチャンネルの体細胞遺伝子変異があることが判明。
■副腎不全
・治療はコートリル朝15mg、夕10mgが一般的。徐放錠が開発された。体重が低下し、血圧が低下した。
■急性副腎不全
・原因はストレス、ステロイドの中断、感染症[63-75%]。
■褐色細胞腫
・悪性:10%、副腎外:10%、家族性:10%。MIBGに10%が陰性。
・遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマ症候群
コハク酸脱水素酵素の遺伝子変異を発見。高率に悪性化しやすい。20-30%が遺伝性であろう。転移がないと悪性・良性の区別がつかない。
■副腎偶発腫瘍
・非機能性;50%。直径>3cm、副腎シンチ取り込み抑制は悪性の可能性が高い。
■subclinical Cushing症候群
・70歳にピーク。女性に多い。肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常を伴う。術後の改善率は60%である。骨折有病率はオッズ比7.3。手術群に悪化例はないが、非手術例では糖尿病、高血圧が悪化している。手術の長期予後はよい。
様々の領域のことを絶えず学習する必要性を実感した。(山本和利)
9月9日、日本内科学会北海道支部主催の第48回生涯教育講演会に参加した。
昭和大学二木芳人氏『感染症の診断と治療、最新の話題』
■難治下する感染症
背景として、医療の進歩により延命、生命維持療法の進歩、医療の場の変化、脳死下移植が増加、骨髄移植が年間4000件を超える、リウマチにおける生物学的製剤、人口の高齢化、様々な合併症(糖尿病、COPD、誤嚥性肺炎)等が挙げられる。肺炎死亡が第3位になった。医療。介護関連肺炎の治療ガイドラインができた。
■耐性菌の話題
・多剤耐性菌(アシネトバクター)の院内感染、「NDM1」新耐性菌を確認(インドから発症)、どんな薬剤も壊すメタロβラクタマーゼが話題となっている。
・インテグロンという複数の耐性遺伝子を効率よく取り込むことができる機序がある。
市中感染に抗菌薬耐性菌が増加している。
・市中感染型MRSA感染症が若年者の皮膚感染が増えている。米国では大流行している。
・市中肺炎では、肺炎球菌、インフルエン桿菌、モラキセラ菌、マイコプラズマ菌、C.pneumoniaeで95%を占める。
・マクロライド薬耐性マイコプラズマが増加している。大人はテトラサイクリンを第一に使う。小児にはニューキノロンを使用は控えること(耐性菌をつくらないため)。マクロライドを使うなら高容量を使う(800mg-1000mg/日)オーグメンチン、フロモックスは大量に使えばかなり有効である(下痢を起こしやすい)。クラリスはインフルエンザ桿菌に耐性が多い(ジスロマックは大丈夫)。
・濃度依存的殺菌:キノロン(一度に大量に投与すること)。
・経口抗菌薬を広範囲に少量を長期間使用することが耐性菌を増やす元凶である!
高知大学横山彰仁氏『慢性気道疾患の診療』
■概観
・COPDと気管支喘息。若いうちは喘息。年取るとCOPD.COPDに対する認知度が低い。認知度を上げるために健康日本21に取り上げられた。
・定義:タバコ暴露、気流閉塞、不可逆なもの。
喘息は喘息症候群と呼んだ方がよい。症状の強さと好酸球性気道炎症と程度の2つの要素で診る。喘息とCOPDは同じ疾患群という「オランダ仮説」がある。どちらか不明のときは喘息として吸入ステロイドを使用すること。
■診断
・COPDは進行性であるが、早期には気付かない。陸で溺れるような辛さがある。タバコに弱い人は早期に禁煙が必要である。症状や画像による診断は遅い。早期発見には肺機能検査がよい。1秒率が70%以下。「肺年齢」という機器が販売されている。
■治療の考え方
・喘息はコントロール状態によって治療する。最小限の薬剤でコントロール状態を維持し、将来のリスクを避ける。まず、吸入ステロイドを使う。
・COPDはいつでも治療可能な疾患である。禁煙、インフルエンザワクチン、併存症の管理が重要。β作動薬よりも先に抗コリン薬を使う。進行したCOPDは増悪をきたす。1秒量<50%、過去に増悪がある例は危険。増悪時のABC.抗菌薬(A)、気管支拡張薬(B)、全身ステロイド(C)
■全身を診る
・3つ以上の併存症があるものが50%。鼻炎、GERDが多い。50歳で1個、65歳で2個。全身性酸化ストレス。糖尿病、心血管疾患(潜在している)、肺炎・肺がん、筋力低下、骨粗鬆症、抑うつ。死因として心血管疾患が多い。頸動脈の動脈硬化が進んでいる(タバコで肺と血管を傷める)。予後を悪化させる。
・COPDの30%に心不全がある。心不全の30%にCOPDがある。選択的β1ブロッカーは安全である。吸入β2刺激薬の使用は要注意である(抗コリン薬がよい)。
■質問
・吸入ステロイドは肺炎のリスクを増す。
・一過性の喘息様症状に吸入ステロイドを使ってもよい。
・喫煙者で呼吸器症状がある患者には、一度呼吸機能検査を勧める。
名古屋大学今井圓裕氏『ネフローゼ症候群の新しい診療指針』
■コホート研究
・巣状分節性腎症;ステロイド抵抗性が60%、パルス・免疫抑制剤が必要、LDLアフェレーシスが有効、日本人の予後は意外とよい。膜性腎症:60%は緩解する。
・微小変化型は再発しやすい。
・死亡例は感染症が原因。過剰な治療が影響。
・ステロイド糖尿病が起こってしまう。
■診療指針
・タンパク尿>3.5g/日(尿たんぱく/尿クレアチニン比>3.5g/gCrでもよい)、浮腫、血清アルブミン<3.0g/dl、脂質異常症。
・思ったよりもステロイド、免疫抑制剤が長期に使われている実態が判明した。
・病態機序としてoverfilling仮説が有力。遠位尿細管でのNa再吸収が亢進。
・治療は、塩分制限:6g/日以下、利尿剤の治療、アルブミン静注は可能な限り避ける、RAS阻害薬を使用。スタチンを使用するかどうかは腎症のタイプによって異なる。
・DVTの予防のためにワーファリンを用いるが、アスピリンについては意見が分かれる。
・膜性腎症の10%に悪性疾患がある。IgGの沈着、足突起のフォスホリパーゼに抗原抗体反応がおこる自己免疫疾患である(日本人では50%)。抗体を減らせば治る。日本人はタンパク尿が少ない。ステロイドパルスは行わない。シクロスポリンを用いる。
・シクロホスファマイドを使用すると、膀胱がんが増える・
・肺炎球菌ワクチン使用、結核のスクリーニング、ニュモシスチス肺炎予防にST合剤を集に2回投与。
・微小変化群:ステロイドが有効だが、パスル療法は不要。再発が多い。
・膜性増殖性腎炎:HCVが関与。確実な治療法はない。
九州大学高柳涼一氏『副腎疾患の最近のTopics』
■原発性アルドステロン症は高血圧の3.3-10%。
・スクリーニングは安静30分後のレニンとアルドステロンを測定。PAC/PRA>200で判定。
・Kチャンネルの体細胞遺伝子変異があることが判明。
■副腎不全
・治療はコートリル朝15mg、夕10mgが一般的。徐放錠が開発された。体重が低下し、血圧が低下した。
■急性副腎不全
・原因はストレス、ステロイドの中断、感染症[63-75%]。
■褐色細胞腫
・悪性:10%、副腎外:10%、家族性:10%。MIBGに10%が陰性。
・遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマ症候群
コハク酸脱水素酵素の遺伝子変異を発見。高率に悪性化しやすい。20-30%が遺伝性であろう。転移がないと悪性・良性の区別がつかない。
■副腎偶発腫瘍
・非機能性;50%。直径>3cm、副腎シンチ取り込み抑制は悪性の可能性が高い。
■subclinical Cushing症候群
・70歳にピーク。女性に多い。肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常を伴う。術後の改善率は60%である。骨折有病率はオッズ比7.3。手術群に悪化例はないが、非手術例では糖尿病、高血圧が悪化している。手術の長期予後はよい。
様々の領域のことを絶えず学習する必要性を実感した。(山本和利)
PR
この記事にコメントする
プロフィール
北海道の地域医療を支える総合診療医の養成を目指す後期研修プログラム「ニポポ」を支える北海道プライマリ・ケアネットワーク代表理事のブログです。
カウンター

