×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
「糖尿病の合併症」
第55回日本糖尿病学会年次学術集会における教育講演の2題をまとめてみた。
■脳卒中について
星野晴彦氏
脳卒中の75%は、脳梗塞である。臨床タイプは3つ。アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ脳梗塞、心原性脳塞栓症の比率は1:1:1となっている。(出血性が20%、くも膜下出血が7%)。アテローム血栓性脳梗塞とラクナ脳梗塞とで患者背景に昔ほど差はなくなってきた。肥満、高コレステロール血症、IGTが増えているためである。糖尿病があると脳梗塞発症率は10年で3倍に上昇する。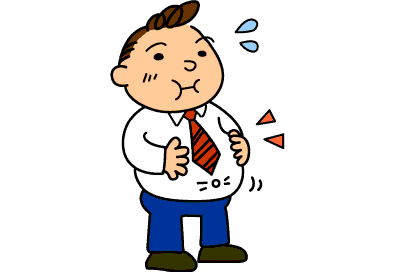
TIA患者は90日以内に10%が脳梗塞になる。そのうち半数は48時間以内である。ABCD2 scoreが重要。(Dは糖尿病)
ABCD2 score (エービーシーディー・スクウェア・スコア)
年齢 (60歳以上で1点)
血圧 (収縮期圧140以上か拡張期圧90以上で1点)
臨床症状 (片麻痺で2点、構音障害のみで1点)
発作持続時間(60分以上で2点、10分から59分で1点、10分未満は0点)
糖尿病 (合併があれば1点)
以上の合計点0-7点で評価する。
心原性脳梗塞:80%は心房細動から。CHADS2 score>2の人は抗凝固薬の適応。(Dは糖尿病)抗凝固薬を服用していた人の方が起こしても予後がよい。発症を1/3に抑える。
CHADS2:CHF(心不全)、HT(高血圧)、Age>75(高齢)、DM(糖尿病)は、それぞれ1点、Stroke/TIA(脳卒中/一過性脳虚血発作)は2点に計算される。
合計点をCHADS2スコアという。
新薬ダビガトランを高容量服用群はワーファリン群より結果がよかった。糖尿病患者においても同様の傾向が見られた。この結果から、糖尿病患者で心房細動があれば即抗凝固療法をする方向に向かいつつある。血圧コントロールはもちろん重要である。
多発動脈硬化は脳梗塞のハイリスクである。ASOの死亡の60%は血管死。ABI<0.9は脳梗塞のハイリスク。高齢者、糖尿病が多い。
BP;130/80mmHg, HbA1C<6.9%,LDL<100を目標として、抗血小板薬を用いるとよい。
■糖尿病腎症の進行予防
古家大祐氏
腎症の有病率が増加している。糖尿病腎症が透析導入原因の第一位である、2型糖尿病患者は増加しており、未受診患者も多い。早期診断が行われていないことも問題である(アルブミン尿の測定)。顕性アルブミン尿+GFR低下群は心血管疾患率が高い。アルブミン尿とGFRの把握が重要である。
予防策として
生活習慣;減量、禁煙、食塩・アルコール制限、運動、厳格な血糖管理、RAS阻害薬の使用が言われている。
早期腎症の緩解を目指すことが大切である。緩解が得られれば心血管リスクを75%減らすことができる。HBa1c<6.9% 、アルブミン尿(-)、血圧<130/80mmHg、脂質低値の4つをコントロールする。しかしながら、罹患期間が長い患者に厳格な血糖コントロールは危険である。血糖値、血圧値は個々の患者によって決めるのがエビデンスである。
冠動脈疾患については、血圧は低過ぎると死亡率が高くなるというエビデンスが出て来ている。収縮期血圧は130-135mmHgがよい(メタ解析から)。最近、RAS阻害薬が第一選択薬でよいかどうか疑問が出されている。スタチンは腎保護作用がある(現在、日本でも研究中)。チーム医療で積極的に集約的治療すると(STENO-2 Trial)死亡率が半減する。とはいっても10年で13%は死亡するのが現状である。
たんぱく制限食で腎症の進行を遅らせることができるかどうか調べたが、通常群とで差を認めなかった。一方、活性炭(クレメジン)は腎症の発症を遅らせる。
第55回日本糖尿病学会年次学術集会における教育講演の2題をまとめてみた。
■脳卒中について
星野晴彦氏
脳卒中の75%は、脳梗塞である。臨床タイプは3つ。アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ脳梗塞、心原性脳塞栓症の比率は1:1:1となっている。(出血性が20%、くも膜下出血が7%)。アテローム血栓性脳梗塞とラクナ脳梗塞とで患者背景に昔ほど差はなくなってきた。肥満、高コレステロール血症、IGTが増えているためである。糖尿病があると脳梗塞発症率は10年で3倍に上昇する。
TIA患者は90日以内に10%が脳梗塞になる。そのうち半数は48時間以内である。ABCD2 scoreが重要。(Dは糖尿病)
ABCD2 score (エービーシーディー・スクウェア・スコア)
年齢 (60歳以上で1点)
血圧 (収縮期圧140以上か拡張期圧90以上で1点)
臨床症状 (片麻痺で2点、構音障害のみで1点)
発作持続時間(60分以上で2点、10分から59分で1点、10分未満は0点)
糖尿病 (合併があれば1点)
以上の合計点0-7点で評価する。
心原性脳梗塞:80%は心房細動から。CHADS2 score>2の人は抗凝固薬の適応。(Dは糖尿病)抗凝固薬を服用していた人の方が起こしても予後がよい。発症を1/3に抑える。
CHADS2:CHF(心不全)、HT(高血圧)、Age>75(高齢)、DM(糖尿病)は、それぞれ1点、Stroke/TIA(脳卒中/一過性脳虚血発作)は2点に計算される。
合計点をCHADS2スコアという。
新薬ダビガトランを高容量服用群はワーファリン群より結果がよかった。糖尿病患者においても同様の傾向が見られた。この結果から、糖尿病患者で心房細動があれば即抗凝固療法をする方向に向かいつつある。血圧コントロールはもちろん重要である。
多発動脈硬化は脳梗塞のハイリスクである。ASOの死亡の60%は血管死。ABI<0.9は脳梗塞のハイリスク。高齢者、糖尿病が多い。
BP;130/80mmHg, HbA1C<6.9%,LDL<100を目標として、抗血小板薬を用いるとよい。
■糖尿病腎症の進行予防
古家大祐氏
腎症の有病率が増加している。糖尿病腎症が透析導入原因の第一位である、2型糖尿病患者は増加しており、未受診患者も多い。早期診断が行われていないことも問題である(アルブミン尿の測定)。顕性アルブミン尿+GFR低下群は心血管疾患率が高い。アルブミン尿とGFRの把握が重要である。
予防策として
生活習慣;減量、禁煙、食塩・アルコール制限、運動、厳格な血糖管理、RAS阻害薬の使用が言われている。
早期腎症の緩解を目指すことが大切である。緩解が得られれば心血管リスクを75%減らすことができる。HBa1c<6.9% 、アルブミン尿(-)、血圧<130/80mmHg、脂質低値の4つをコントロールする。しかしながら、罹患期間が長い患者に厳格な血糖コントロールは危険である。血糖値、血圧値は個々の患者によって決めるのがエビデンスである。
冠動脈疾患については、血圧は低過ぎると死亡率が高くなるというエビデンスが出て来ている。収縮期血圧は130-135mmHgがよい(メタ解析から)。最近、RAS阻害薬が第一選択薬でよいかどうか疑問が出されている。スタチンは腎保護作用がある(現在、日本でも研究中)。チーム医療で積極的に集約的治療すると(STENO-2 Trial)死亡率が半減する。とはいっても10年で13%は死亡するのが現状である。
たんぱく制限食で腎症の進行を遅らせることができるかどうか調べたが、通常群とで差を認めなかった。一方、活性炭(クレメジン)は腎症の発症を遅らせる。
「死者を弔う」
医療に対する文化の影響を研究する分野に医療人類学というものがある。その第一人者がアーサー・クラインマンである。彼は精神科領域の研究を台湾で行い、この分野の先駆けとなった。
クラインマンは、著書『病いの語り』(誠信書房、1996年)の中で、「患うという経験の型はどこでも見られるが、その患うことが何を意味し、その経験をどのように生き、その経験にどうように対処し扱うかは、実に様々である。」とし、それを1)文化的表象、2)集合的経験、3)個人的経験、に区分した。
クラインマンは、医療人類学者としての経験・研究から、「病いの語りは、どのように人生の問題が作り出され、制御され、意味あるものにされてゆくかを教える。」と述べている。
患う・悩む(suffering)とは「困惑の問い」「秩序とコントロールの問い」であり、患者を医療化に向かわせる。そして、それを次の3つに区分した。こうすることで良好な患者医師関係が構築しやすくなる。
1) 病い(illness):患者独特なもの
2) 疾患(disease):治療者の視点
• 徴候に翻訳
• 生物医学モデル
3) 病気(sickness):社会的な関係
クラインマンは、「慢性の病いは、異なった個人によって生きられた経験である。」と考えている。しかしながら、医療従事者の説明モデルによって、「医学の声が生活世界の声をかき消す。」ことが多い。そこで、「患者の言うことに耳を傾けよ、患者は診断を語っているのだ。」と訴え、患者の思いを拾い上げる説明モデル(解釈モデル)を聴くことを提案した。それには、
• 障害の原因は何か?
• なぜそのとき発症したのか?
• 体への影響は?
• どんな経過を辿るのか?
• どうようにコントロールできるのか?
• 生活への影響は?
• 治療への希望
• 治療への恐れ
等の質問が含まれる。これはOSCEにおける医療面接の聴取すべき項目に盛り込まれている。
生きている時ばかりでなく、死者にも文化は影響を与える。それがよくわかるものとして『父の初七日』(ワン・ユーリン監督、台湾、2009年)を紹介したい(日本映画では伊丹十三監督の『お葬式』がある)。
舞台はクラインマンが研究をした台湾の片田舎である。突然の父親の訃報を聞き、台湾で働く女性主人公が帰省する。病院で心停止しても、酸素吸入を受けながら救急車で家に運ばれ、そこで死亡宣告を受ける(台湾では家で死ぬことが最高の幸せと考えるから)。そしてその地域の伝統的な道教式の葬儀が執り行われることになる。占いで葬儀は7日後と決まり、それまでに、泣き女が出てきたり、音楽隊の演奏があったりとお祭りのような騒ぎになる。そんな中で過ごす7日間に父親と過ごした思い出が蘇る。本当に涙を流すのは4ヶ月後であった・・・。
ある地域の医療機関では、在宅ケアを受けてなくなられた患者宅に49日になると訪問をして、患者家族の悲嘆ケアをしているという。地域医療の現場では、その地域特有の文化を考慮しながら医療展開をするという魅力も兼ね備えている。
医療に対する文化の影響を研究する分野に医療人類学というものがある。その第一人者がアーサー・クラインマンである。彼は精神科領域の研究を台湾で行い、この分野の先駆けとなった。
クラインマンは、著書『病いの語り』(誠信書房、1996年)の中で、「患うという経験の型はどこでも見られるが、その患うことが何を意味し、その経験をどのように生き、その経験にどうように対処し扱うかは、実に様々である。」とし、それを1)文化的表象、2)集合的経験、3)個人的経験、に区分した。
クラインマンは、医療人類学者としての経験・研究から、「病いの語りは、どのように人生の問題が作り出され、制御され、意味あるものにされてゆくかを教える。」と述べている。
患う・悩む(suffering)とは「困惑の問い」「秩序とコントロールの問い」であり、患者を医療化に向かわせる。そして、それを次の3つに区分した。こうすることで良好な患者医師関係が構築しやすくなる。
1) 病い(illness):患者独特なもの
2) 疾患(disease):治療者の視点
• 徴候に翻訳
• 生物医学モデル
3) 病気(sickness):社会的な関係
クラインマンは、「慢性の病いは、異なった個人によって生きられた経験である。」と考えている。しかしながら、医療従事者の説明モデルによって、「医学の声が生活世界の声をかき消す。」ことが多い。そこで、「患者の言うことに耳を傾けよ、患者は診断を語っているのだ。」と訴え、患者の思いを拾い上げる説明モデル(解釈モデル)を聴くことを提案した。それには、
• 障害の原因は何か?
• なぜそのとき発症したのか?
• 体への影響は?
• どんな経過を辿るのか?
• どうようにコントロールできるのか?
• 生活への影響は?
• 治療への希望
• 治療への恐れ
等の質問が含まれる。これはOSCEにおける医療面接の聴取すべき項目に盛り込まれている。
生きている時ばかりでなく、死者にも文化は影響を与える。それがよくわかるものとして『父の初七日』(ワン・ユーリン監督、台湾、2009年)を紹介したい(日本映画では伊丹十三監督の『お葬式』がある)。
舞台はクラインマンが研究をした台湾の片田舎である。突然の父親の訃報を聞き、台湾で働く女性主人公が帰省する。病院で心停止しても、酸素吸入を受けながら救急車で家に運ばれ、そこで死亡宣告を受ける(台湾では家で死ぬことが最高の幸せと考えるから)。そしてその地域の伝統的な道教式の葬儀が執り行われることになる。占いで葬儀は7日後と決まり、それまでに、泣き女が出てきたり、音楽隊の演奏があったりとお祭りのような騒ぎになる。そんな中で過ごす7日間に父親と過ごした思い出が蘇る。本当に涙を流すのは4ヶ月後であった・・・。
ある地域の医療機関では、在宅ケアを受けてなくなられた患者宅に49日になると訪問をして、患者家族の悲嘆ケアをしているという。地域医療の現場では、その地域特有の文化を考慮しながら医療展開をするという魅力も兼ね備えている。
「5月の三水会」
5月16日、札幌医大で、ニポポ研修医の振り返りの会が行われた。大門伸吾医師が司会進行。後期研修医:3名。 初期研修5名。他:5名。
研修医から振り返り6題。
ある研修医。外来患者のリストを検討。百日咳と抗体価を測定して診断。抗菌薬は治療に必須ではない。高尿酸血症を治療しているが、ザイロリックの用量はいかにすべきか。米国のガイドラインはザイロリックを使用してはいけないというふうに書きかえられている。ペニシリンアレルギーのある人の蜂窩織炎。本当にペニシリンアレルギーがあるのかどうか、突き詰めた方がよい。
88才女性。嘔吐、喘鳴、SpO2低下。脳出血後遺症(VPシャント)。誤嚥性肺炎と診断し治療した。できるだけ延命して欲しいという家人の希望あり。脳出血時と同じ症状なので、MRI撮影を希望(前回CTは異常なしであったがMRIで異常が見つかったから)。脳外科医に依頼してVPシャントのバブルを調整してMRI撮影をした。今後、どう対応したらよいか。コメント:娘の感情を受け入れて、娘を落ち着かせる。今後の未来予測を正直に話して方策を立てる。チームで対応する。
ある研修医。外来リスト。ゴルフで背筋肉離れ、17歳の女子の圧迫骨折、等を経験した。受診患者のうち整形外科手術になる患者は限られている。かなりの患者は総合医が診ることができるのではないかという印象をもった。コメント:外傷、受傷機転を知ることが重要。
58歳男性。感冒後、全身倦怠感と微熱、腰痛。XPで「疲労」と診断。その後、腰痛が悪化し、夜間救急車で受診。ボルタレン座薬を使い、帰宅させようとしたが、体動時の痛みが強いため、入院させた。L3/4に圧痛。LDH:387,CRP:2.3.腰部CTでL2/3に骨融解像。胸部CT,腫瘍マーカーから小細胞がんが示唆された。コメント:Red flagサインを知ることが大事。50歳を超えた患者の初めての腰痛、夜間痛、安静時痛、等。検査の特性(感度、特異度)を知ること。病歴によっては感染症も考慮しなければならない。
ある研修医。小児科研修。入院患者は喘息、肺炎、クループ、胃腸炎が多い。
咳、呼吸困難、咽頭痛で救急搬送された17歳男性。37.4℃、呼吸数:20/分、SpO2:95%。HR:112/分。唾液を頻回に吐いていた。過換気症候群を疑った。夜間のため技師さんを呼ばずXPを撮るのは控えた。心電図、血液ガスは異常なかった。ここで、気胸、肺炎、急性喉頭蓋炎が鑑別に挙がる。XPとCTで縦隔気腫が判明。入院し経過観察となった。早期にXPを撮るべきであった。コメント:病歴を振り返ると、最終診断を教えている。技師さんの負担だけでなく、患者さんのもつ疾患の緊急度、重症度を優先することが大切である。
ある初期研修医。肺腺癌の76歳女性。イレッサ適応であったが使用拒否。疼痛が悪化し肋骨転移、転移多数が判明。そこで、イレッサを使用することを承諾。患者への説明が難しいと感じた。悪い知らせを伝えるSPIKESという6段階方略があることがわかった。その解説(環境の設定、患者の認識を評価、患者の求めを確認、患者に知識と情報を提供、患者の感情に共感をこめる、方略をまとめる)。コメント:うまいと言われている指導医の説明場面を沢山見ること。
ある初期研修医。97歳女性。胸部違和感、息切れ、全身倦怠感で救急外来受診。BP:
125/85mmHg,体温:36.4℃、呼吸数:24回/分。SpO2:95%。Coarse crackleあり。念のため、心電図、採血、胸部XPで心筋梗塞を除外したいと思った。心電図:III、aVFでST上昇。XPで肺うっ血像があったが、血液検査結果がでるまで心筋梗塞を考慮しなかった。重篤感がないため、心筋梗塞を考慮しなかった。研修してから初めての心筋梗塞であった。その後、初期治療計画を立てさせてもらい、ニトロ舌下、血管確保、利尿薬の投与を行った。コメント:高齢者、糖尿病、女性は心筋梗塞でも胸痛が出にくい。臍から上の痛みで受診したら心電図を撮ること。歩いてきた心筋梗塞とくも膜下血腫は見逃しやすい。
ある初期研修医。胃痛を訴える28歳男性。救急外来。朝から胃痛。便の色はふつう。整形外科でNSAIDを処方されている。これまで何度も腹痛で受診している。そのため最初はIBSを考慮した。身体診察で心窩部から右下腹部に圧痛。反跳痛あり。血液検査、CTで虫垂炎と診断し、手術にもっていった。初めて最初から手術まで経過を追えた虫垂炎であった。緊急性のある疾患の除外が大切。Alvarado scoreでスコアリングできる。この事例は6点であったため、CTを撮った。疑ったらまずエコー。小児の発熱、嘔吐、腹痛、腹部膨満では常に虫垂炎を考慮する。
年度が変わり新しい研修医が参加してくれ、雰囲気がいい意味で一新された。ヒヤリ・ハット事例から学ぶことは多いと再認識した勉強会であった。(山本和利)
5月16日、札幌医大で、ニポポ研修医の振り返りの会が行われた。大門伸吾医師が司会進行。後期研修医:3名。 初期研修5名。他:5名。
研修医から振り返り6題。
ある研修医。外来患者のリストを検討。百日咳と抗体価を測定して診断。抗菌薬は治療に必須ではない。高尿酸血症を治療しているが、ザイロリックの用量はいかにすべきか。米国のガイドラインはザイロリックを使用してはいけないというふうに書きかえられている。ペニシリンアレルギーのある人の蜂窩織炎。本当にペニシリンアレルギーがあるのかどうか、突き詰めた方がよい。
88才女性。嘔吐、喘鳴、SpO2低下。脳出血後遺症(VPシャント)。誤嚥性肺炎と診断し治療した。できるだけ延命して欲しいという家人の希望あり。脳出血時と同じ症状なので、MRI撮影を希望(前回CTは異常なしであったがMRIで異常が見つかったから)。脳外科医に依頼してVPシャントのバブルを調整してMRI撮影をした。今後、どう対応したらよいか。コメント:娘の感情を受け入れて、娘を落ち着かせる。今後の未来予測を正直に話して方策を立てる。チームで対応する。
ある研修医。外来リスト。ゴルフで背筋肉離れ、17歳の女子の圧迫骨折、等を経験した。受診患者のうち整形外科手術になる患者は限られている。かなりの患者は総合医が診ることができるのではないかという印象をもった。コメント:外傷、受傷機転を知ることが重要。
58歳男性。感冒後、全身倦怠感と微熱、腰痛。XPで「疲労」と診断。その後、腰痛が悪化し、夜間救急車で受診。ボルタレン座薬を使い、帰宅させようとしたが、体動時の痛みが強いため、入院させた。L3/4に圧痛。LDH:387,CRP:2.3.腰部CTでL2/3に骨融解像。胸部CT,腫瘍マーカーから小細胞がんが示唆された。コメント:Red flagサインを知ることが大事。50歳を超えた患者の初めての腰痛、夜間痛、安静時痛、等。検査の特性(感度、特異度)を知ること。病歴によっては感染症も考慮しなければならない。
ある研修医。小児科研修。入院患者は喘息、肺炎、クループ、胃腸炎が多い。
咳、呼吸困難、咽頭痛で救急搬送された17歳男性。37.4℃、呼吸数:20/分、SpO2:95%。HR:112/分。唾液を頻回に吐いていた。過換気症候群を疑った。夜間のため技師さんを呼ばずXPを撮るのは控えた。心電図、血液ガスは異常なかった。ここで、気胸、肺炎、急性喉頭蓋炎が鑑別に挙がる。XPとCTで縦隔気腫が判明。入院し経過観察となった。早期にXPを撮るべきであった。コメント:病歴を振り返ると、最終診断を教えている。技師さんの負担だけでなく、患者さんのもつ疾患の緊急度、重症度を優先することが大切である。
ある初期研修医。肺腺癌の76歳女性。イレッサ適応であったが使用拒否。疼痛が悪化し肋骨転移、転移多数が判明。そこで、イレッサを使用することを承諾。患者への説明が難しいと感じた。悪い知らせを伝えるSPIKESという6段階方略があることがわかった。その解説(環境の設定、患者の認識を評価、患者の求めを確認、患者に知識と情報を提供、患者の感情に共感をこめる、方略をまとめる)。コメント:うまいと言われている指導医の説明場面を沢山見ること。
ある初期研修医。97歳女性。胸部違和感、息切れ、全身倦怠感で救急外来受診。BP:
125/85mmHg,体温:36.4℃、呼吸数:24回/分。SpO2:95%。Coarse crackleあり。念のため、心電図、採血、胸部XPで心筋梗塞を除外したいと思った。心電図:III、aVFでST上昇。XPで肺うっ血像があったが、血液検査結果がでるまで心筋梗塞を考慮しなかった。重篤感がないため、心筋梗塞を考慮しなかった。研修してから初めての心筋梗塞であった。その後、初期治療計画を立てさせてもらい、ニトロ舌下、血管確保、利尿薬の投与を行った。コメント:高齢者、糖尿病、女性は心筋梗塞でも胸痛が出にくい。臍から上の痛みで受診したら心電図を撮ること。歩いてきた心筋梗塞とくも膜下血腫は見逃しやすい。
ある初期研修医。胃痛を訴える28歳男性。救急外来。朝から胃痛。便の色はふつう。整形外科でNSAIDを処方されている。これまで何度も腹痛で受診している。そのため最初はIBSを考慮した。身体診察で心窩部から右下腹部に圧痛。反跳痛あり。血液検査、CTで虫垂炎と診断し、手術にもっていった。初めて最初から手術まで経過を追えた虫垂炎であった。緊急性のある疾患の除外が大切。Alvarado scoreでスコアリングできる。この事例は6点であったため、CTを撮った。疑ったらまずエコー。小児の発熱、嘔吐、腹痛、腹部膨満では常に虫垂炎を考慮する。
年度が変わり新しい研修医が参加してくれ、雰囲気がいい意味で一新された。ヒヤリ・ハット事例から学ぶことは多いと再認識した勉強会であった。(山本和利)
「医療市場の開放」
グローバル化を目指して、様々な産業分野の市場を国外勢力に解放すべきか、国内産業を保護すべく開放を見送るべきかの議論が盛んである。医療について、日本医師会は開放反対の声明を出している。ここでグローバル化を考える上で参考になる書籍を紹介したい。
『中国化する日本』(与那覇 潤著、文藝春秋、2011年)である。著者は、日本史を専門とする若手研究者である。学術用語を用いずに、若者言葉を交えて解説しており分かりやすく、引き込まれてしまう。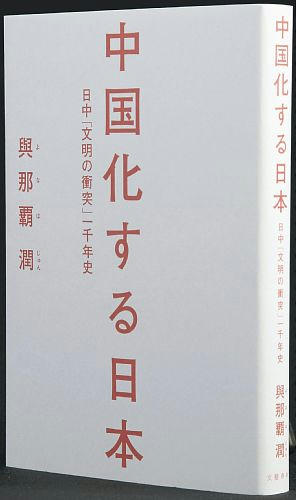
著者のいう「中国化」とは中国の宋で導入された社会のことを指している。それは今の言葉でいうと「グローバル化」に近い。中国史を1か所区切るなら唐と宋の間で切れるとする立場である。その根拠は、宋時代に入って1)貴族制度を全廃して皇帝独裁政治を始めた、2)経済や社会を徹底的に自由化する代わりに、政治の秩序は一極支配によって維持する仕組みを作った、からであり、その後、新たな要素は加わっていないという。
この中国化という概念で、日本の歴史を論評している。源平合戦は、守旧派勢力の源氏と新しいことをやろうとした(中国化)平氏のと争いと観る。それ以降の時代も全て「中華文明」対「日本文明」という概念で論評してゆく。
中華文明の特徴は
1.権威と権力の一致(皇帝が政治的権力を掌握)
2.政治と道徳の一体化(政治と道徳の「正しさ」の一致)
3.地位の一貫した上昇(皇帝が行う科挙で官僚を選抜)
4.市場ベースの秩序の流動化(農村共同体秩序の解体)
5.人間関係のネットワーク化(父系血族コネクションの優先)
この反対が「江戸時代の日本」となる。
モンゴル来襲、江戸時代、明治維新、昭和日本、「大東亜戦争」、戦後民主主義、平成日本、等、これまでとは違う「再江戸時代化」対「中国化」の概念で一刀両断に論じきってしまっている。
「再江戸時代化」にしても、「中国化」にしてもそれぞれに短所と長所を抱えている。日本はどの方向へ向かうべきなのか?医療はどうあるべきなのか?今、大き岐路に立っていることは間違いない。
グローバル化を目指して、様々な産業分野の市場を国外勢力に解放すべきか、国内産業を保護すべく開放を見送るべきかの議論が盛んである。医療について、日本医師会は開放反対の声明を出している。ここでグローバル化を考える上で参考になる書籍を紹介したい。
『中国化する日本』(与那覇 潤著、文藝春秋、2011年)である。著者は、日本史を専門とする若手研究者である。学術用語を用いずに、若者言葉を交えて解説しており分かりやすく、引き込まれてしまう。
著者のいう「中国化」とは中国の宋で導入された社会のことを指している。それは今の言葉でいうと「グローバル化」に近い。中国史を1か所区切るなら唐と宋の間で切れるとする立場である。その根拠は、宋時代に入って1)貴族制度を全廃して皇帝独裁政治を始めた、2)経済や社会を徹底的に自由化する代わりに、政治の秩序は一極支配によって維持する仕組みを作った、からであり、その後、新たな要素は加わっていないという。
この中国化という概念で、日本の歴史を論評している。源平合戦は、守旧派勢力の源氏と新しいことをやろうとした(中国化)平氏のと争いと観る。それ以降の時代も全て「中華文明」対「日本文明」という概念で論評してゆく。
中華文明の特徴は
1.権威と権力の一致(皇帝が政治的権力を掌握)
2.政治と道徳の一体化(政治と道徳の「正しさ」の一致)
3.地位の一貫した上昇(皇帝が行う科挙で官僚を選抜)
4.市場ベースの秩序の流動化(農村共同体秩序の解体)
5.人間関係のネットワーク化(父系血族コネクションの優先)
この反対が「江戸時代の日本」となる。
モンゴル来襲、江戸時代、明治維新、昭和日本、「大東亜戦争」、戦後民主主義、平成日本、等、これまでとは違う「再江戸時代化」対「中国化」の概念で一刀両断に論じきってしまっている。
「再江戸時代化」にしても、「中国化」にしてもそれぞれに短所と長所を抱えている。日本はどの方向へ向かうべきなのか?医療はどうあるべきなのか?今、大き岐路に立っていることは間違いない。
プロフィール
北海道の地域医療を支える総合診療医の養成を目指す後期研修プログラム「ニポポ」を支える北海道プライマリ・ケアネットワーク代表理事のブログです。
カウンター

