×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
3月21日、札幌医科大学において三水会が行われた。参加者は9名。大門伸吾医師が司会進行。後期研修医:5名。初期研修医1名。他:6名。
研修医から振り返り5題。病棟、外来で受け持った患者について供覧後、SEAを発表。
ある研修医。外来症例の報告。60代の男性。長谷川式20点。認知症患者への対応はどのようにしたらよいか。コメント:まず器質的疾患を除外する。ガイドラインを読み込むことも大切。
急性増悪した間質性肺炎。70歳台の男性.橋本病の既往。労作性呼吸困難、SpO2:84% .吸気時fine crackle陽性。咳がひどい。XP;すりガラス陰影。BiPAPを試行。ステロイドパルスとエンドキサンパルスを実施。家族は蘇生を希望した。家族には疾患に対する理解が不足していた。質問に答え、傾聴するしかなかった。1カ月で死亡。
ある研修医。外来経験。院内スタッフがインフルエンザは落ち着いた。認知症患者の湯たんぽによる低温熱傷(見た目より深い層に達している)。不明熱で見つかった膵臓嚢胞性腫瘍。発作性心房細動への対応。
胃癌術後で食事摂取ができない患者さん。関係性を構築するのが難しかった。SpO2が急速に悪化。意識レベルが低下。「そんなに頑張らなくていいよ」という言葉が出て来た。家族の表情は固かった。医師として口にしてよいのかどうかと反省した。こういうセリフを言えるような関係性をつくりたい。49日にお悔やみ訪問する予定。
ある研修医。外来経験。20歳台男性の胸部痛で狭心症の精査(本当に必要なのか?)40歳台女性の体重減少。40歳代男性の肉眼的血尿。
80歳代女性。発熱、咳そう、喀痰。認知症の夫と二人暮らし。足関節の痛みが出現。偽痛風と診断された。全身倦怠感を訴えたので、患者背景を探った。夫に問題行動があることがわかった。家の中は荒れ放題であった。そこに介入して問題が解決し始めたら症状も軽快した(患者さんのうれし泣きを初めて見た)。「病気を診るのではなく、患者さんを診る」を再認識した。
ある研修医。外来経験。帯状疱疹後神経痛の患者への処方。中年男性の肛門周囲膿瘍(コメント:HIVを疑い性行動を訊く)。肺塞栓症。糖尿病性壊疽。家族歴をもつ肺塞栓症。
80歳代女性の意識障害。頸部骨折術後。糖尿病で血糖降下剤内服中。嘔吐、失禁あり。会話がおかしい。頻脈。血糖値が824mg/dl以上。WBC;23,000、人工関節部位の感染とそれによる敗血症であった。その治療により意識障害は改善した。
(山本和利が)会議で途中退席したため、1名分割愛。
スキルアップセミナー終了後、市内の居酒屋でニポポプログラムが終了となる研修医の壮行会を行った。それぞれ道内の医療機関で総合医(総合内科)として就職する。(山本和利)
研修医から振り返り5題。病棟、外来で受け持った患者について供覧後、SEAを発表。
ある研修医。外来症例の報告。60代の男性。長谷川式20点。認知症患者への対応はどのようにしたらよいか。コメント:まず器質的疾患を除外する。ガイドラインを読み込むことも大切。
急性増悪した間質性肺炎。70歳台の男性.橋本病の既往。労作性呼吸困難、SpO2:84% .吸気時fine crackle陽性。咳がひどい。XP;すりガラス陰影。BiPAPを試行。ステロイドパルスとエンドキサンパルスを実施。家族は蘇生を希望した。家族には疾患に対する理解が不足していた。質問に答え、傾聴するしかなかった。1カ月で死亡。
ある研修医。外来経験。院内スタッフがインフルエンザは落ち着いた。認知症患者の湯たんぽによる低温熱傷(見た目より深い層に達している)。不明熱で見つかった膵臓嚢胞性腫瘍。発作性心房細動への対応。
胃癌術後で食事摂取ができない患者さん。関係性を構築するのが難しかった。SpO2が急速に悪化。意識レベルが低下。「そんなに頑張らなくていいよ」という言葉が出て来た。家族の表情は固かった。医師として口にしてよいのかどうかと反省した。こういうセリフを言えるような関係性をつくりたい。49日にお悔やみ訪問する予定。
ある研修医。外来経験。20歳台男性の胸部痛で狭心症の精査(本当に必要なのか?)40歳台女性の体重減少。40歳代男性の肉眼的血尿。
80歳代女性。発熱、咳そう、喀痰。認知症の夫と二人暮らし。足関節の痛みが出現。偽痛風と診断された。全身倦怠感を訴えたので、患者背景を探った。夫に問題行動があることがわかった。家の中は荒れ放題であった。そこに介入して問題が解決し始めたら症状も軽快した(患者さんのうれし泣きを初めて見た)。「病気を診るのではなく、患者さんを診る」を再認識した。
ある研修医。外来経験。帯状疱疹後神経痛の患者への処方。中年男性の肛門周囲膿瘍(コメント:HIVを疑い性行動を訊く)。肺塞栓症。糖尿病性壊疽。家族歴をもつ肺塞栓症。
80歳代女性の意識障害。頸部骨折術後。糖尿病で血糖降下剤内服中。嘔吐、失禁あり。会話がおかしい。頻脈。血糖値が824mg/dl以上。WBC;23,000、人工関節部位の感染とそれによる敗血症であった。その治療により意識障害は改善した。
(山本和利が)会議で途中退席したため、1名分割愛。
スキルアップセミナー終了後、市内の居酒屋でニポポプログラムが終了となる研修医の壮行会を行った。それぞれ道内の医療機関で総合医(総合内科)として就職する。(山本和利)
PR
2月15日、札幌医科大学において三水会が行われた。参加者は13名。稲熊良仁助教が司会進行。後期研修医:4名。初期研修医1名。他:6名。
研修医から振り返り4題。病棟、外来で受け持った患者について供覧後、SEAを発表。
ある研修医。外来症例の報告。小児インフルエンザが蔓延。小児科・発熱外来化している。点滴できる抗インフルエンザ剤が著功。インフルエンザへの過剰な処置を要求してくる。母親に予防の啓発、教育が大切。牛に突かれて転倒。慢性硬膜下血腫から水腫になった症例。
66歳の男性。山好きなターミナル患者さん。胃癌術後、2年。胃癌の転移・再発。アルコール依存症傾向。低栄養とジョクソウで入院した既往がある。入院精査をしたがはっきりした異常を指摘されない。6kgの体重減少。食欲不振が強く、経胃管注入量が増えると嘔吐を誘発する。透視で通過障害あり。CEA、ALP高値。骨転移を考える。IVHポートで対応。信頼関係ができていない。良好な医師患者関係が構築できない。病室へ足が遠のく。難しい宿題を出されている感じ。病棟カンファにかけている。
ある研修医。外来。除雪後の腰痛。インフルエンザ。「口の中が塩辛い」患者。腰痛で経過観察された腎盂腎炎。「排便時に上胸部がしびれる」男性。
胸水貯留の62歳男性。狭心症、糖尿病あり。土木工事に従事歴あり。肩が痛む喫煙者。咳と労作時呼吸困難。胸部XPで胸水を指摘される。CTで胸水、無気肺。呼吸音が減弱。貧血、低栄養、心房細動あり。血性胸水であり、クラスVで悪性中皮腫を疑った。精査加療のため転院待ちとなった。貧血、胸水が悪化。そのうちにせん妄が出現。急変しBiPAP装着したまま転院。死亡し剖検の結果、肺がんであった。転院のタイミングはどうであったのか。診断についての振り返りがあった。
途中、高橋知事との会に参加するため中座。
ある研修医。23歳男性。胸部違和感で受診し、心電図でST上昇があった。どうやって心筋炎を鑑別するのか?シャウグ・ストラウス症候群を受け持つ。胸部違和感があり、上部消化管内視鏡で食道は異常なし。狭心症ではないのか?インスリンを自己中断している糖尿病患者の高血糖。ただインスリンを渡せばいいのか?
41歳女性。喘息発作と肥満(160cm,125kg)、脂質異常症、脂肪肝。喫煙者。インフルエンザ罹患(タミフル内服)後、喘息大発作となる。SpO2:77%(PaO2;52mmHg)緊急入院。人工呼吸器装着。
喘息と肥満の関係について考察。スレロイド吸入合剤についての振り返り。アドヒアランスがあったのか。
来年度からはこの振り返りの会をもう少しシスタティックにすることを計画している。(山本和利)
研修医から振り返り4題。病棟、外来で受け持った患者について供覧後、SEAを発表。
ある研修医。外来症例の報告。小児インフルエンザが蔓延。小児科・発熱外来化している。点滴できる抗インフルエンザ剤が著功。インフルエンザへの過剰な処置を要求してくる。母親に予防の啓発、教育が大切。牛に突かれて転倒。慢性硬膜下血腫から水腫になった症例。
66歳の男性。山好きなターミナル患者さん。胃癌術後、2年。胃癌の転移・再発。アルコール依存症傾向。低栄養とジョクソウで入院した既往がある。入院精査をしたがはっきりした異常を指摘されない。6kgの体重減少。食欲不振が強く、経胃管注入量が増えると嘔吐を誘発する。透視で通過障害あり。CEA、ALP高値。骨転移を考える。IVHポートで対応。信頼関係ができていない。良好な医師患者関係が構築できない。病室へ足が遠のく。難しい宿題を出されている感じ。病棟カンファにかけている。
ある研修医。外来。除雪後の腰痛。インフルエンザ。「口の中が塩辛い」患者。腰痛で経過観察された腎盂腎炎。「排便時に上胸部がしびれる」男性。
胸水貯留の62歳男性。狭心症、糖尿病あり。土木工事に従事歴あり。肩が痛む喫煙者。咳と労作時呼吸困難。胸部XPで胸水を指摘される。CTで胸水、無気肺。呼吸音が減弱。貧血、低栄養、心房細動あり。血性胸水であり、クラスVで悪性中皮腫を疑った。精査加療のため転院待ちとなった。貧血、胸水が悪化。そのうちにせん妄が出現。急変しBiPAP装着したまま転院。死亡し剖検の結果、肺がんであった。転院のタイミングはどうであったのか。診断についての振り返りがあった。
途中、高橋知事との会に参加するため中座。
ある研修医。23歳男性。胸部違和感で受診し、心電図でST上昇があった。どうやって心筋炎を鑑別するのか?シャウグ・ストラウス症候群を受け持つ。胸部違和感があり、上部消化管内視鏡で食道は異常なし。狭心症ではないのか?インスリンを自己中断している糖尿病患者の高血糖。ただインスリンを渡せばいいのか?
41歳女性。喘息発作と肥満(160cm,125kg)、脂質異常症、脂肪肝。喫煙者。インフルエンザ罹患(タミフル内服)後、喘息大発作となる。SpO2:77%(PaO2;52mmHg)緊急入院。人工呼吸器装着。
喘息と肥満の関係について考察。スレロイド吸入合剤についての振り返り。アドヒアランスがあったのか。
来年度からはこの振り返りの会をもう少しシスタティックにすることを計画している。(山本和利)
1月18日、札幌医科大学において三水会が行われた。参加者は13名。大門伸吾医師が司会進行。後期研修医:5名。初期研修医2名。他:6名。
研修医から振り返り5題。病棟、外来で受け持った患者について供覧後、SEAを発表。
ある研修医。放射線科研修で画像全体をみる癖がついた。病棟患者を持たないと楽。88歳女性。ペースメーカー外来で、全身倦怠感を訴える。SSS、心原性脳梗塞、高血圧。肺炎、心不全という診断がついた。治療で改善。施設にもどって即38℃。CRP:5.0。1ヶ月後に退院し、以前の施設に戻る。発熱があるというだけで施設に戻れないというのは不合理ではないか。家族を入れてのカンファランスをもった。介護老人保健施設についての報告。医療保険が使えない。他院の外来を受診すると、施設の10割負担となる検査項目が幾つかある。健康で安価の薬を飲んでいる患者が最適。手のかかる人は置きたくない。スタッフが不安定な患者を診たくないという印象を持った。
コメント:このような患者をどこの施設で内科の医師が診るかが問題になってゆくだろう。
ある研修医。寒い。気温-23℃。国外に居住していた64歳男性。肺がんのターミナル・ケア。糖尿病。ふらつき、めまいで帰国し精査。頭部CTで腫瘍あり。左肺に肺がんを発見された。病状はStage IV。脳にγナイフ治療のみ。脳浮腫にリンデロンを使用し、糖尿病があるためインスリンを使用。入院加療。病室でインターネットをしたい(海外に居る知人と連絡するため)。外出して自宅で喫煙、インターネットをしていた。底冷えがする家で、ターミナルを迎える状況としては不適切であった。背部痛、腹満感。胸水が出現。麻薬を使用して、疼痛対応している。
クリニカル・パール:死ぬ時は自宅というのは短絡的である。 それなりの環境が必要である。
ある研修医。68歳女性。甲状腺癌のターミナル・ケア。頸部腫瘍。気管切開。自宅は寒い、お金が乏しい、夫は病気である、という理由で外泊をしたがらない。疼痛管理はできたが、コミュニケーションが難しい。筆談も難しい。外泊の話も進まない。進行が早く、2カ月で死亡となった。この患者にどんなことができただろうか?
ある研修医。62歳女性。全身倦怠感。眼瞼結膜蒼白。舌乳頭委縮なし。爪の変形なし。Hb:6.3g/dl,MCV:105,徐々に小球化してきている。CFで上行結腸眼があった。術後、食事が摂れず、十二指腸狭窄によるものであった。その後、Hb6.4,MCV 119と大球性貧血となった。フェリチン:1030、ビタミンB12,葉酸:正常。虫卵なし。抗内因子抗体陰性。輸血で当場を凌いだ。最終診断がついていない。何だろう?
コメント:ビタミンB12や葉酸をトライしてみる。MDSはないか。マルクを繰り返す。
ある研修医。糖尿病あり、脳梗塞後にイレウスを起こした78歳男性。脳梗塞後、腹部膨満。心房細動。腹部CTで二ボーを認める。最終的に麻痺性イレウスと診断した。
クリニカル・パール:脳梗塞患者におけるイレウスでは、腸間膜血栓症等を否定する必要がある。
コメント:どういう患者に腸間膜血栓症を疑うべきなのか、が重要である。
ここでイレウスの復習をした。腸管壊死の有無:腹痛増強、発熱、頻脈、腹膜刺激症状、乳酸値の増加、白血球の増加、等で判断する。CTの感度:15-100%、特異度85%。
この時期になって来年度の研修先、就職先が決まってきた(医師が激減している市立病院の内科や教育病院の総合内科)。今回はターミナル症例が多かった。受け持ち症例をエクセルにまとめて提示してもらった中に、複雑な日常疾患がたくさん見られた。(山本和利)
研修医から振り返り5題。病棟、外来で受け持った患者について供覧後、SEAを発表。
ある研修医。放射線科研修で画像全体をみる癖がついた。病棟患者を持たないと楽。88歳女性。ペースメーカー外来で、全身倦怠感を訴える。SSS、心原性脳梗塞、高血圧。肺炎、心不全という診断がついた。治療で改善。施設にもどって即38℃。CRP:5.0。1ヶ月後に退院し、以前の施設に戻る。発熱があるというだけで施設に戻れないというのは不合理ではないか。家族を入れてのカンファランスをもった。介護老人保健施設についての報告。医療保険が使えない。他院の外来を受診すると、施設の10割負担となる検査項目が幾つかある。健康で安価の薬を飲んでいる患者が最適。手のかかる人は置きたくない。スタッフが不安定な患者を診たくないという印象を持った。
コメント:このような患者をどこの施設で内科の医師が診るかが問題になってゆくだろう。
ある研修医。寒い。気温-23℃。国外に居住していた64歳男性。肺がんのターミナル・ケア。糖尿病。ふらつき、めまいで帰国し精査。頭部CTで腫瘍あり。左肺に肺がんを発見された。病状はStage IV。脳にγナイフ治療のみ。脳浮腫にリンデロンを使用し、糖尿病があるためインスリンを使用。入院加療。病室でインターネットをしたい(海外に居る知人と連絡するため)。外出して自宅で喫煙、インターネットをしていた。底冷えがする家で、ターミナルを迎える状況としては不適切であった。背部痛、腹満感。胸水が出現。麻薬を使用して、疼痛対応している。
クリニカル・パール:死ぬ時は自宅というのは短絡的である。 それなりの環境が必要である。
ある研修医。68歳女性。甲状腺癌のターミナル・ケア。頸部腫瘍。気管切開。自宅は寒い、お金が乏しい、夫は病気である、という理由で外泊をしたがらない。疼痛管理はできたが、コミュニケーションが難しい。筆談も難しい。外泊の話も進まない。進行が早く、2カ月で死亡となった。この患者にどんなことができただろうか?
ある研修医。62歳女性。全身倦怠感。眼瞼結膜蒼白。舌乳頭委縮なし。爪の変形なし。Hb:6.3g/dl,MCV:105,徐々に小球化してきている。CFで上行結腸眼があった。術後、食事が摂れず、十二指腸狭窄によるものであった。その後、Hb6.4,MCV 119と大球性貧血となった。フェリチン:1030、ビタミンB12,葉酸:正常。虫卵なし。抗内因子抗体陰性。輸血で当場を凌いだ。最終診断がついていない。何だろう?
コメント:ビタミンB12や葉酸をトライしてみる。MDSはないか。マルクを繰り返す。
ある研修医。糖尿病あり、脳梗塞後にイレウスを起こした78歳男性。脳梗塞後、腹部膨満。心房細動。腹部CTで二ボーを認める。最終的に麻痺性イレウスと診断した。
クリニカル・パール:脳梗塞患者におけるイレウスでは、腸間膜血栓症等を否定する必要がある。
コメント:どういう患者に腸間膜血栓症を疑うべきなのか、が重要である。
ここでイレウスの復習をした。腸管壊死の有無:腹痛増強、発熱、頻脈、腹膜刺激症状、乳酸値の増加、白血球の増加、等で判断する。CTの感度:15-100%、特異度85%。
この時期になって来年度の研修先、就職先が決まってきた(医師が激減している市立病院の内科や教育病院の総合内科)。今回はターミナル症例が多かった。受け持ち症例をエクセルにまとめて提示してもらった中に、複雑な日常疾患がたくさん見られた。(山本和利)
11月16日、札幌医科大学において三水会が行われた。参加者は12名。稲熊良仁助教が司会進行。後期研修医:5名。他:7名。
研修医から振り返り6題。今回から、病棟、外来で受け持った患者について供覧することにした。
ある研修医。小児科で研修中。感冒性腸炎、急性上気道炎、喘息が多い。ときに水痘、手足口病。水痘についての議論で盛り上がった。外来、新生児、乳児健診、ワクチン、子育てサロン(ロール・プレイもする)、病後児デイサービス、産婦人科外来で研修。母親とコミュニケーションをとることやその対応が難しい。

1歳児男児の母親に「子供の歯磨きにフッ素塗布をした方がよいか?」と質問された。母子保健上、法的な滋氏義務はない。幼稚園、保育園での89%が実施。札幌市、旭川市は実施していない。虫歯予防には水道水へのフッ化物添加、フッ化物塗布、砂糖制限が重要。日本は虫歯が多い(2.4本)。
予防接種の話題。任意接種のワクチンの接種率がよくない。日本の保健行政は、各自治体の裁量にまかされている。そのため地域格差がある。地域の医療関係者が連携して取り組む必要がある。
ある研修医。抗凝固薬再開につき悩んだ一例。75歳男性。発熱、悪寒。前立腺がん(膀胱瘻)、Af、脳梗塞。軽度黄疸あり、貧血あり。CTで胆嚢肥大。胆管炎。CHADS2スコアが4点。ヘパリンを使用後、下血が出現。前立腺がんの直腸浸潤と診断。ストマは作らないことになった。出血のリスクを冒してまで抗凝固薬は使用しない。胆管炎は軽快し、リハビリをしている。何もしないで経過観察をしたい。
クリニカル・パール:患者・家族に抗凝固薬のリスクを十分に説明することが必要である。
ある研修医。あるCPA蘇生後の一例。68歳女性。全身浮腫。CPAで救急搬送となった。蘇生後、CVカテーテルを挿入。今後の栄養をどうするか。家族の意見は延命医療を拒否。院内カンファランス(医師のみ)の結果、気管切開術を行い、PEGを造設した。本当は徹底的に患者家族と話し合うべきであった。患者家族の意向に沿えなかった。最初のコミュニケーショ不足が指摘された。
ある研修医。夜間当直中に63歳男性がめまい、腹痛で受診。苦悶様で体をくねらせる。腹部は平坦、圧痛なしで、急性胃腸炎と診断した。休ませてほしいと患者がいうので点滴を依頼した。3日後、その患者さんがICUに入院している。術後腸閉塞であった。排便、嘔吐はなかった。BUN:77, Cre;5.7。癒着性イレウス、敗血症性ショック、腎前性腎不全。
ここで腸閉塞のレビューが披露された。
クリニカル・パール:高齢者の腹痛には重症疾患をいれるべきである。下痢だからといって腸閉塞を否定してはいけない。腸閉塞は臍周囲の痛みで発症する。高齢者救急受診の原因で多いのは胆道疾患と小腸閉塞である。
ある研修医。訪問診療について。これにより家のことがよくわかる。85歳女性。酒飲みの長男と二人暮らし。整形外科と内科の薬が重なっている。むくみあり、Hb:4.7g/dl。(鉄剤を中止したため)
89歳の独居女性。胸部大動脈瘤持ち。イレウスで入院。退院後、ある朝、死亡しているのを発見された。
82歳女性。認知症で動けないという理由で往診依頼。風呂に3年間入っていない。本人は困っていない。入院を勧めたが拒否。
80歳女性。脳梗塞後遺症で寝たきり。ベッドから転落。頭部CTで硬膜下血腫。
84歳男性。心原生脳梗塞。CPAで救急搬送。心電図から心筋梗塞によるAf。翌日、意識は全く正常になっていた。しなしながらその後、ベッドから転落。低血圧。収縮期雑音あり。心エコーで心室中か隔穿孔であった。
クリニカル・パール:医療から隔絶された家もまだまだある。やっぱり心臓疾患は怖い。
ある研修医。コントロールに難渋している糖尿病患者。76歳女性。脳梗塞の既往。インスリン治療していてもHbA1c:10%。精査で膵がんは否定的。デイサービスで定期的運動をしてもらった。その日の血糖値はよいが、往診した日の血糖値は悪い。しっかり食事療法はしているが、御代りは自由である。「自分だけではできない」患者。
相談症例。96歳の意識のない女性。PEGを作らないと療養病棟に移れない場合、PEGを作るべきか? 生物学的禁忌、社会学的適用。
今回は様々な症例が提示され、議論も盛り上がった。受け持ち症例をエクセルにまとめて提示する方法は今後も継続してゆきたい。
研修医から振り返り6題。今回から、病棟、外来で受け持った患者について供覧することにした。
ある研修医。小児科で研修中。感冒性腸炎、急性上気道炎、喘息が多い。ときに水痘、手足口病。水痘についての議論で盛り上がった。外来、新生児、乳児健診、ワクチン、子育てサロン(ロール・プレイもする)、病後児デイサービス、産婦人科外来で研修。母親とコミュニケーションをとることやその対応が難しい。
1歳児男児の母親に「子供の歯磨きにフッ素塗布をした方がよいか?」と質問された。母子保健上、法的な滋氏義務はない。幼稚園、保育園での89%が実施。札幌市、旭川市は実施していない。虫歯予防には水道水へのフッ化物添加、フッ化物塗布、砂糖制限が重要。日本は虫歯が多い(2.4本)。
予防接種の話題。任意接種のワクチンの接種率がよくない。日本の保健行政は、各自治体の裁量にまかされている。そのため地域格差がある。地域の医療関係者が連携して取り組む必要がある。
ある研修医。抗凝固薬再開につき悩んだ一例。75歳男性。発熱、悪寒。前立腺がん(膀胱瘻)、Af、脳梗塞。軽度黄疸あり、貧血あり。CTで胆嚢肥大。胆管炎。CHADS2スコアが4点。ヘパリンを使用後、下血が出現。前立腺がんの直腸浸潤と診断。ストマは作らないことになった。出血のリスクを冒してまで抗凝固薬は使用しない。胆管炎は軽快し、リハビリをしている。何もしないで経過観察をしたい。
クリニカル・パール:患者・家族に抗凝固薬のリスクを十分に説明することが必要である。
ある研修医。あるCPA蘇生後の一例。68歳女性。全身浮腫。CPAで救急搬送となった。蘇生後、CVカテーテルを挿入。今後の栄養をどうするか。家族の意見は延命医療を拒否。院内カンファランス(医師のみ)の結果、気管切開術を行い、PEGを造設した。本当は徹底的に患者家族と話し合うべきであった。患者家族の意向に沿えなかった。最初のコミュニケーショ不足が指摘された。
ある研修医。夜間当直中に63歳男性がめまい、腹痛で受診。苦悶様で体をくねらせる。腹部は平坦、圧痛なしで、急性胃腸炎と診断した。休ませてほしいと患者がいうので点滴を依頼した。3日後、その患者さんがICUに入院している。術後腸閉塞であった。排便、嘔吐はなかった。BUN:77, Cre;5.7。癒着性イレウス、敗血症性ショック、腎前性腎不全。
ここで腸閉塞のレビューが披露された。
クリニカル・パール:高齢者の腹痛には重症疾患をいれるべきである。下痢だからといって腸閉塞を否定してはいけない。腸閉塞は臍周囲の痛みで発症する。高齢者救急受診の原因で多いのは胆道疾患と小腸閉塞である。
ある研修医。訪問診療について。これにより家のことがよくわかる。85歳女性。酒飲みの長男と二人暮らし。整形外科と内科の薬が重なっている。むくみあり、Hb:4.7g/dl。(鉄剤を中止したため)
89歳の独居女性。胸部大動脈瘤持ち。イレウスで入院。退院後、ある朝、死亡しているのを発見された。
82歳女性。認知症で動けないという理由で往診依頼。風呂に3年間入っていない。本人は困っていない。入院を勧めたが拒否。
80歳女性。脳梗塞後遺症で寝たきり。ベッドから転落。頭部CTで硬膜下血腫。
84歳男性。心原生脳梗塞。CPAで救急搬送。心電図から心筋梗塞によるAf。翌日、意識は全く正常になっていた。しなしながらその後、ベッドから転落。低血圧。収縮期雑音あり。心エコーで心室中か隔穿孔であった。
クリニカル・パール:医療から隔絶された家もまだまだある。やっぱり心臓疾患は怖い。
ある研修医。コントロールに難渋している糖尿病患者。76歳女性。脳梗塞の既往。インスリン治療していてもHbA1c:10%。精査で膵がんは否定的。デイサービスで定期的運動をしてもらった。その日の血糖値はよいが、往診した日の血糖値は悪い。しっかり食事療法はしているが、御代りは自由である。「自分だけではできない」患者。
相談症例。96歳の意識のない女性。PEGを作らないと療養病棟に移れない場合、PEGを作るべきか? 生物学的禁忌、社会学的適用。
今回は様々な症例が提示され、議論も盛り上がった。受け持ち症例をエクセルにまとめて提示する方法は今後も継続してゆきたい。
10月22日、足寄町我妻病院において三水会が行われた。札幌組はバスをチャーターし、途中トイレ休憩を2回入れて4時間半で到着。参加者は22名。

はじめに山本和利の挨拶。続いて、我妻病院のケアマネージャーの中村さんから、「地域で研修医を育てる」という講演を拝聴した。地域医療の楽しさを伝え、人を育てることを目標としている。受け入れ学生数はこれまでに36名。研修医は22名。研修医指導や仕事を楽しんでいることが伝わってくる発表であった。

グループ・ワーク「医療と介護・福祉の連携」を3グループで話し合った。KJ法を使用。「相手がわからない。接点がない。」「温度差、価値観の違い。」「人手不足。」「システムがない。」などの阻害因子が出た。定期的に会合を開いてお互いを知ることから始めなければならない、という結論に落ち着いた。

足寄町福祉課寺本圭祐さん(社会福祉士)から「地域住民を守る」という講演。足寄町の高齢化率は33%。つり橋を渡らないと行きつかない家や馬と共に生きる家、鹿柵の中で鹿と共存する崩壊寸前の家を紹介。外風呂と外トイレの家がまだまだある。崩壊寸前の家に帰りたい脳梗塞後遺症患者さんの事例を多職種で検討し、家族と話し合いもした。結局、「本人はどうしたいのか?」が問題となり、本人と面談。「1回も家を見ていない」という話がでたので、「いよいよ家へ」帰った。自宅で寛いだ後、素直に「また病院へ」戻った。「髪を切って施設へ行く」と、納得された様子で決意を語った。
行政としては、「だれのためなのかを考える」、「それぞれが単独では何も解決しない」ことを学んだ。今回は、医療機関と連携がうまくいったため。現在、循環型支援システムを模索している。
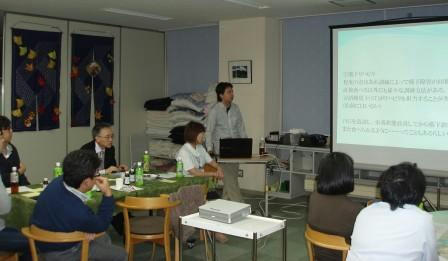
研修医から振り返り2題。その前に司会役の松浦武志医師からSEAの説明。
ある研修医。54歳女性。糖尿病、脂質異常症あり。HbA1c:12%でインスリン導入の依頼あり。都会に娘が居住。統合失調症で一人暮らしである。今回三回目の入院。これまでインスリン導入を拒否。入院すると血糖値も改善していた。糖尿病コントロールの経緯が書かれていない。患者へインスリン導入について了承を得ないで紹介している。インスリン導入の必要性を説明したが、最終的には導入を見送った。紹介してきた医師に、同意をとってもらいたかったことを記載して郵送した。
娘にもっと関わってもらってはどうか、電話で主治医に確認してはどうか、食事の宅配サービスを利用する、という意見がでた。
ある研修医。嚥下障害、摂食不良の高齢者。認知症で寝たきりの70歳代男性。胃癌手術後、ASO、心不全。誤嚥性肺炎、踵の壊死で入院。脳の委縮。尿道カテーテル留置状態。
痰からみが強く、SaO2が低下したため、食事を止めた。ここで栄養管理のレヴュー。多くの家族は、栄養管理についてどうしたらよいか「わからない」と答える。最終的に、点滴ののみで、家族の持ち込み食可とした。その後、家族から病院食を食べさせたいと提案あり。数日後、永眠された。
クリニカル・パール:患者さんと医療者側で認識の差を自覚することが大切である。
今回は、理学療法士、栄養士、看護師、社会福祉士等、様々な職種の方々が参加してくれたため、医師だけでは思いつかない意見が出た。多職種によるカンファランスの重要性を再認識させられた。

今回は1泊1,070円の青年の家を利用。簡易ベッドに自分でシーツや枕カバーを付けて就寝。学生時代に泊まったユースホステルを思い出した。翌日、玄関前で記念写真を撮ってバスで4時間半かけての帰宅の途についた。(山本和利)
はじめに山本和利の挨拶。続いて、我妻病院のケアマネージャーの中村さんから、「地域で研修医を育てる」という講演を拝聴した。地域医療の楽しさを伝え、人を育てることを目標としている。受け入れ学生数はこれまでに36名。研修医は22名。研修医指導や仕事を楽しんでいることが伝わってくる発表であった。
グループ・ワーク「医療と介護・福祉の連携」を3グループで話し合った。KJ法を使用。「相手がわからない。接点がない。」「温度差、価値観の違い。」「人手不足。」「システムがない。」などの阻害因子が出た。定期的に会合を開いてお互いを知ることから始めなければならない、という結論に落ち着いた。
足寄町福祉課寺本圭祐さん(社会福祉士)から「地域住民を守る」という講演。足寄町の高齢化率は33%。つり橋を渡らないと行きつかない家や馬と共に生きる家、鹿柵の中で鹿と共存する崩壊寸前の家を紹介。外風呂と外トイレの家がまだまだある。崩壊寸前の家に帰りたい脳梗塞後遺症患者さんの事例を多職種で検討し、家族と話し合いもした。結局、「本人はどうしたいのか?」が問題となり、本人と面談。「1回も家を見ていない」という話がでたので、「いよいよ家へ」帰った。自宅で寛いだ後、素直に「また病院へ」戻った。「髪を切って施設へ行く」と、納得された様子で決意を語った。
行政としては、「だれのためなのかを考える」、「それぞれが単独では何も解決しない」ことを学んだ。今回は、医療機関と連携がうまくいったため。現在、循環型支援システムを模索している。
研修医から振り返り2題。その前に司会役の松浦武志医師からSEAの説明。
ある研修医。54歳女性。糖尿病、脂質異常症あり。HbA1c:12%でインスリン導入の依頼あり。都会に娘が居住。統合失調症で一人暮らしである。今回三回目の入院。これまでインスリン導入を拒否。入院すると血糖値も改善していた。糖尿病コントロールの経緯が書かれていない。患者へインスリン導入について了承を得ないで紹介している。インスリン導入の必要性を説明したが、最終的には導入を見送った。紹介してきた医師に、同意をとってもらいたかったことを記載して郵送した。
娘にもっと関わってもらってはどうか、電話で主治医に確認してはどうか、食事の宅配サービスを利用する、という意見がでた。
ある研修医。嚥下障害、摂食不良の高齢者。認知症で寝たきりの70歳代男性。胃癌手術後、ASO、心不全。誤嚥性肺炎、踵の壊死で入院。脳の委縮。尿道カテーテル留置状態。
痰からみが強く、SaO2が低下したため、食事を止めた。ここで栄養管理のレヴュー。多くの家族は、栄養管理についてどうしたらよいか「わからない」と答える。最終的に、点滴ののみで、家族の持ち込み食可とした。その後、家族から病院食を食べさせたいと提案あり。数日後、永眠された。
クリニカル・パール:患者さんと医療者側で認識の差を自覚することが大切である。
今回は、理学療法士、栄養士、看護師、社会福祉士等、様々な職種の方々が参加してくれたため、医師だけでは思いつかない意見が出た。多職種によるカンファランスの重要性を再認識させられた。
今回は1泊1,070円の青年の家を利用。簡易ベッドに自分でシーツや枕カバーを付けて就寝。学生時代に泊まったユースホステルを思い出した。翌日、玄関前で記念写真を撮ってバスで4時間半かけての帰宅の途についた。(山本和利)
プロフィール
北海道の地域医療を支える総合診療医の養成を目指す後期研修プログラム「ニポポ」を支える北海道プライマリ・ケアネットワーク代表理事のブログです。
カウンター

